離婚時の親権・養育費・親子交流などに関する法改正(2026年5月施行)
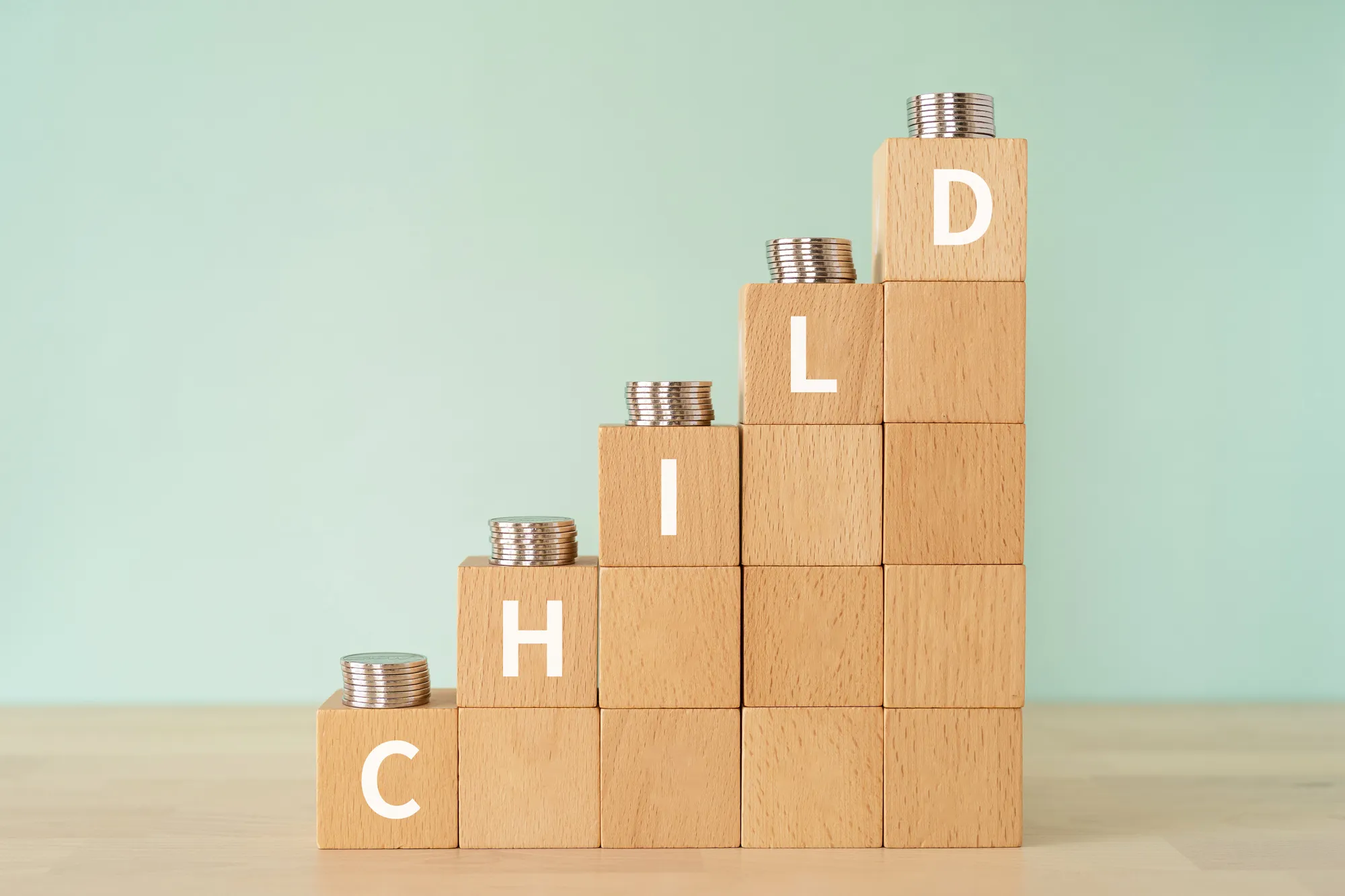
2024 年12月に、民法などの離婚に関するルールを定めた法律が改正されました。
今回の法改正では、親権、養育費、親子の交流、財産分与に関するルールが見直されるとともに、親が子どもを養育する責務が明確化されました。
なお、本改正については、2025年10月31日に2026年(令和8年)4月1日から施行されることが決定されています。
※本ページに記載の条文は、断りのない限り、すべて2024年12月の改正後の新しい条文です。
目次
1 親権
(1)共同親権
親権とは、親が子どものために監護・教育を行ったり、子どもの財産を管理したりする、親の権限・義務のことです(民法820条)。
両親の婚姻中は、父母双方が親権者として共同で親権を行使しますが、従来の民法では、離婚後は父母どちらかだけが親権者となり、離婚する際に、父母どちらかを親権者と決めなければなりませんでした。
2024 年の民法改正で、離婚の際に、父母双方を親権者とする(共同親権)ことも、今までどおり、父母どちらかだけが親権者となるように単独親権の定めをすることも、いずれも選択できるようになります(民法819条)。
協議離婚の場合は、両親の協議の結果に基づいて、離婚届に、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを記載して、双方が署名して提出します(同条1項)。
協議がまとまらなかった場合は、家庭裁判所に調停や裁判を申し立てることになります。
裁判では、両親と子どもの関係や、父と母との関係など様々な事情を考慮した上で、子どものためという観点から、裁判所が、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。調停や裁判の手続では、家庭裁判所は、父母それぞれから意見を聴かなければならず、子どもの意思を把握するよう努めなければなりません(同条3項)。
ただし、次のような場合には、家庭裁判所は、共同親権ではなく、必ず単独親権の定めをすることとされています(同条7項)。
- 子どもに対する虐待のおそれがある場合
- DV等、父母が共同して親権を行うことが困難な場合
離婚後、状況が大きく変わり、子どものために親権者を変更する必要があるときは、家庭裁判所に申立てを行って認められれば、親権者の変更をすることができます。
また、DV等で対等な立場での合意形成が困難なため、やむを得ず共同親権で協議離婚したようなケースでは、離婚後に、親権者の変更を申し立てて単独親権に変更してもらうことが考えられます(同条8項)。
もっとも、従来、親権者の変更のハードルは高かったため、法改正後もなかなか親権者の変更は認められない可能性が高いです。なるべく、離婚の際に、子どもの将来を考えて離婚することが望ましいでしょう。
(2)共同親権の行使方法
ア 親権行使のルール
今回の法改正では、婚姻中や、離婚後共同親権などで、父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されました(民法824条の2)。
- 親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
- 次の場合は、親権の単独行使ができます。
- 養育や教育等に関する日常の行為をするとき
- 子どものために緊急の事情があるとき
- 特定の事項について、家庭裁判所の手続で1人を親権行使の代表者にすることができます。
イ 養育や教育等に関する日常の行為の例
養育や教育等に関する日常の行為とは、日常生活の中で生じる監護教育に関する行為で、子どもに重大な影響を与えないものをいいます。例えば、日常の行為に当たる例、当たらない例としては、次のような場合があるとされています。
<養育や教育等に関する日常の行為に当たる例>
- 食事や服装
- 短期間の旅行
- 心身に重大な影響を与えない医療行為(軽症での通院、予防接種など)
- 習い事
- 高校生のアルバイトの許可
<養育や教育等に関する日常の行為に当たらず、親権の共同行使が必要な例>
- 子どもの転居(監護者とともに転居する場合など)
- 進学や未成年での就職
- 心身に重大な影響を与える医療行為(緊急でない入院・手術への同意など)
- 子ども名義の財産について親が行う決定
ウ 子どものために緊急の事情があるときの例
子どものために緊急の事情があるときとは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては親権の行使が間に合わず、子どものためにならない事態に陥るおそれがある場合をいいます。急迫の事情があるときは、日常の行為にあたらない重大な事柄についても、父母の一方が単独で親権を行使することができます。
例えば、急迫の事情の例としては、次のような場合があります。
- 児童虐待、子どもへのDVからの避難(転居を含む)
- 緊急の医療行為
- 入学試験の結果発表後に入学手続の期限が迫っているような場合
(3)監護
監護とは、実際に子どもと同居して、子どもの養育や教育をする権限と責任をいいます。
今回の法改正では、監護者が子どもの養育や教育等について親権者と同一の権利義務を有し、1人で監護権を行使できることが明記され、離婚後の子どもの監護の分担に関するルールが明確化されました(民法824条の3)。
離婚後の父母双方を親権者とした場合であっても、その一方を監護者と定めることで、子どもの監護をその一方に委ねることになります(同条1項)。
監護の分担の定めをした場合、監護者は、子どもの進学や未成年での就職の決定など、養育や教育等に関する日常の行為に当たらない決定を、監護者でない親権者の同意なく行うことができます。監護者でない親権者は、監護者が子どもの監護をすることを妨害してはなりませんが、監護者による監護を妨害しない形で、親子交流の機会などに、子どもの監護をすることは支障ありません(同条2項)。
2 養育費
(1)裁判を経ない養育費の差押えが可能に
従来の民法では、同居親と別居親の間で養育費の取り決めをしていたとしても、別居親が養育費の支払を怠ったときに別居親の財産を差し押さえるためには、公正証書や調停調書、審判などの手続と、差押えの手続とで、2段階の裁判所の手続が必要でした。
今回の改正により、養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与されるため、債務名義がなくても、養育費の取決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差押えの手続を申し立てることができるようになります(民法306条、308条の2)。
この先取特権が付与される養育費の範囲は、法務省令で定めるものとされていますが、2025年8月29日に法務省から子供1人あたり月額8万円とする方針が示されています。
(2)法定養育費の新設
従来の民法では、父母の協議や家庭裁判所の手続により養育費の額を取り決めなければ、養育費を請求することができませんでした。
今回の改正により、離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、離婚のときから引き続き子どもの監護を行う同居親は、別居親に対して、一定額の「法定養育費」を請求することができるようになります。また、法定養育費の支払がされないときは、差押えを申し立てることができます(民法766条の3)。
法定養育費の額は、法務省令で定めるものとされていますが、2025年8月29日に法務省から子供1人あたり月額2万円とする方針が示されています。
(3)裁判手続きの利便性向上
養育費に関する裁判所の手続では、各自の収入を基礎として、養育費の額を算定することとなります。そこで、今回の改正では、手続をスムーズに進めるために、家庭裁判所が、当事者に対して収入情報の開示を命じることができることとしています。
また、養育費を差押えるための裁判所の手続では、1回の申立てで、財産の開示から差押えまでの一連の手続を同時に申請できるようになります(民事執行法167条の17、人事訴訟法34条の3、家事事件手続法152条の2)。
- 財産開示手続:養育費の支払義務者は、その保有する財産を開示しなければならない
- 情報提供命令:市区町村に対し、養育費の支払義務者の給与情報の提供を命じる
- 債権差押命令:判明した給与債権を差し押さえる
これにより、財産を開示させた段階で、相手方に差押えの意思が分かってしまい、財産を隠されてしまう事態を防ぐことができるようになりました。
3 親子交流(面会交流)
(1)親子交流の調停・裁判中の親子交流の実施
家庭裁判所は、調停・審判において、別居した親、離婚した親と子どもの親子交流について、子どものためを最優先に考えて取り決めを行います。その際の調査や調整に当たっては、手続中に親子交流を試行的に実施し、その状況や結果を把握することが望ましい場合があります。
そこで、今回の改正では、親子交流の試行的実施に関する制度を設けました(人事訴訟法34条の4、家事事件手続法152条の3)。
(2)離婚前の別居中の親子交流の実施
婚姻中に、様々な理由により、親が子どもと別居することがあります。しかし、従来は、離婚後の面会交流については規定されているものの、離婚前で別居中の親子交流に関する規定はありませんでした。
そこで、今回の改正では、従来の離婚後の面会交流と同じように、別居中の親と子どもとの親子交流を行うことや、面会交流と同様の裁判所の手続が使用できるように規定されました(民法817条の13)。
(3)祖父母、兄弟姉妹等との面会交流の実施
従来の民法では、父母以外の親族(例えば祖父母等)と子どもとの交流に関する規定はありませんでした。しかし、例えば、祖父母等と子どもとの間に親子関係に準ずる親密な関係があったような場合には、交流を継続することが子どもにとって望ましい場合があります。
そこで、今回の改正では、子どものために特に必要なときに限り、家庭裁判所は、父母以外の親族と子どもとの交流を実施するよう定めることができるようになりました(民法766条の2)。
また、子どもが親以外の親族と交流をするかどうかの申立てを行う権限があるのは、原則として親ですが、例えば、親の一方が死亡したり行方不明になったりした場合などは、親族が家庭裁判所に申立てをすることができるようになります。
4 財産分与(民法768条)
(1)請求期間が5年に延長
財産分与とは、夫婦が婚姻中に共に築いた財産を、離婚の際にそれぞれ分け合う制度です。財産分与は、まずは夫婦の協議によって決めますが、協議が成立しない場合は、家庭裁判所に対して財産分与の請求をすることができます。
なお、今までは財産分与の請求をすることができる期間が、離婚後2年までに制限されていましたが、今回の改正で、離婚後5年まで請求できるようになります(民法768条2項)。
(2)考慮要素の明確化
これまで民法では、財産分与に当たってどのような事情を考慮すべきかが、明確に規定されていませんでした。
そこで、今回の改正では、財産分与の目的が各自の財産上の公平を図ることであることを明らかにした上で、以下の考慮要素を例として示しています(民法768条3項)。
<明示された考慮要素の例>
- 婚姻中に築いた財産の額
- 財産の取得又は維持についての夫婦各自の貢献の程度(原則1/2ずつ)
- 婚姻期間の長さ
- 婚姻中の生活水準
- 婚姻中の協力及び扶助の状況
- 夫婦それぞれの年齢、心身の状況、職業、収入
このうち「財産の取得又は維持についての各自の寄与の程度」については、直接収入を得るための就労だけでなく、家事労働や育児の分担など様々な性質のものが含まれることから、寄与の程度は、原則として夫婦対等(1/2ずつ)とされています。
(3)財産開示命令
財産分与の裁判手続では、分与の対象となる財産の種類や金額を明らかにする必要があります。そこで、今回の改正では、手続をスムーズに進めるために、家庭裁判所が、当事者に対して財産情報の開示を命じることができることとしています(人事訴訟法34条の3第2項)。
そして、家庭裁判所の開示命令について、正当な理由なくその情報を開示せず、又は虚偽の情報を開示したときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処するとされています(人事訴訟法34条の3第3項)。
5 再婚に伴う養子縁組
(1)親権者の明確化
未成年者が養子になった場合には、養親がその子どもの親権者となり、実親は親権を失います。
離婚後に、実親の片方が再婚し、再婚相手を養親とする養子縁組(いわゆる連れ子養子)がされた場合には、養親(再婚相手)とその配偶者である実親が親権者となります(民法818条3項)。この場合、実父母の離婚後に共同親権の定めをしていたとしても、他方の親権者は親権を失うことになります。
(2)共同親権者が養子縁組に同意しない場合の裁判手続
15 歳未満の子どもが養子縁組をするときは、養子縁組前の子どもの親権者が法定代理人として養子縁組の手続を行います(民797条1項)。
従来の民法では、父母双方が親権者のときに、その意見対立を調整するための規定がなく、父母の意見が一致しなければ養子縁組をすることができませんでした。
今回の改正では、養子縁組の手続に関する父母の意見対立を家庭裁判所が調整するための手続が新設されました(民797条3項)。
家庭裁判所は、子どものため特に必要があると認めるときに限り、父母の一方を養子縁組についての親権行使者に指定します。親権行使者は、単独で、養子縁組の手続を行うことができます。これにより、片親が親権行使者に指定されると、片親と養親だけで養子縁組の手続を行うことができるようになる仕組みです。
6 まとめ
以上のとおり、離婚に関するルールを定めた法律が改正されました。離婚の時期や定め方など、従来の民法とは異なるルールで離婚することが望ましい場合も希望に副わない場合も考えられるため、個別具体的な事例に応じて、弁護士の判断を仰ぐことが望ましいです。
G&Sでは、協議段階から裁判までの流れを踏まえて、経験豊富な弁護士が個別具体的な事情に応じた最適な方法を考えて、離婚協議や調停等を行います。親権・監護権から養育費や親子交流については、G&Sまでお気軽にご相談ください。






